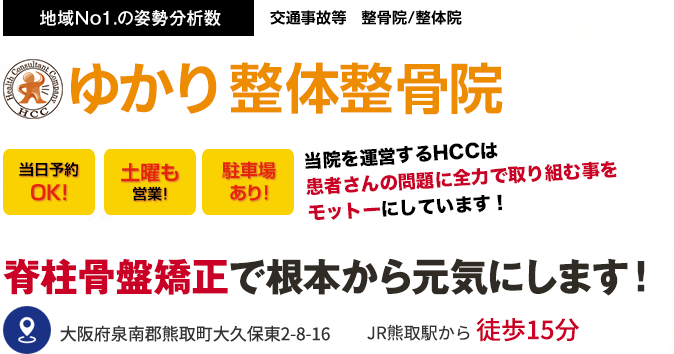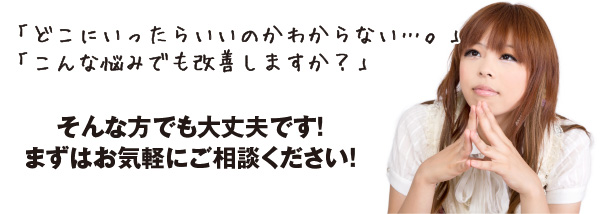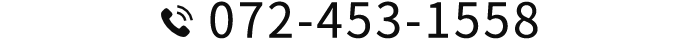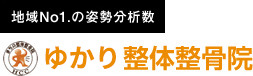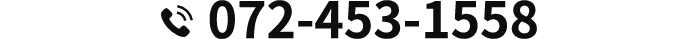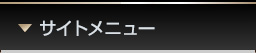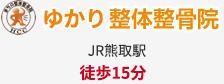泉南郡熊取町 ゆかり整体整骨院が解説する 認知症初期症状
2024.07.24
認知症の初期症状4選
①物忘れ
物忘れは誰にでもあるものです。しかし、頻度が高くなってきた場合は認知症の初期症状の可能性が高いです。
例えば
何度も同じことを聞いてくる、話してくる
ゴミの回収日を忘れてゴミを出す日を間違える
同じものを何度も買ってくる
料理の味付けが変わる
置き忘れや忘れ物が増える
②気分が落ち込む
認知機能が低下すると、精神的に落ち込んだり、混乱したりする症状がみられます。
例えば
少しのことで怒るようになった
財布を置いた場所がわからなくなり人に盗まれたと言い出す
活気がなくなった
趣味や日々の習慣への興味がなくなってきた
③集中力の低下
認知症の初期症状として集中力が低下する場合があります。
例えば
計算がミスが増えた
運転中ぼーっとする
会話やドラマのストーリーの流れを追えなくなる
手芸や家事など集中力して最後まで出来なくなった
④時間や場所の感覚が乱れる
今いる場所、時間などの感覚が乱れることで、普段の生活習慣が行えなくなる場合があります。
認知症がある程度進行してから起きる症状ではありますが、初期段階でも起きる可能性があるため周りに注意してみてもらいましょう!
具体的には
今の日付がわからない
さっきまで電話していた人の名前がわからない
近所でも道に迷ってしまうことがある
思い当たる点が3つ以上ある方は要注意!
無料ご予約はコチラ
Googleマップはコチラをクリック

泉南郡熊取町にある ゆかり整体整骨院が解説する 避けてほしい人の特徴
2024.07.08
どんなに立派な雰囲気に見えても、避けてほしい人の特徴をお伝えします
一言で表すと【他人を尊重できない人】
FullSizeRender
例えば、食事に行った際にその場にいない人の話をする人。しかも若干斜め上から批判的なことを言い出します。
最後にはマウントを取ろうとするので要注意!
こういう他人を尊重できない人は他人を損得勘定でしか見ていないですよね。
つまりあなたにメリットがないと判断したら態度が変わったり、冷たくされたり、偉そうに見下すような言い方をしてきます。
次にそういう人の見分け方をお伝えします。
今から言う3つをよく観察して下さい。
1つ目
忙しくなった途端に機嫌が悪くなる
態度に出て、言葉が荒くなる
2つ目
ギブ&テイクやシェアなどという感覚を持ち合わせていない
3つ目
人を素直に褒めない
なんなら褒めない
この中の2つ当てはまる人とは距離を取った方がいいです。
あなたにとって貴重な時間とエネルギーを吸い取られてしまいます。
ネットからの予約はコチラ
マップ情報はコチラ
泉南郡熊取町にある ゆかり整体整骨院が解説する メンタルが強い人の口癖
2024.07.06
【最年少の責任者が伝える】
メンタルが強い人の口癖3選
メンタルが強い人って共通の口癖を持っているって知ってた?
3つ目はメンタルが強い人が必ず言っている口癖だからメンタル強くしたいなら必ず最後まで見て
1つ目
「自分は自分 他人は他人」
メンタルが強い人って自分自身をきちんと持っているから他人と比べることがないんです
だからこそ自分は自分と考えることができて目標を達成するためには何をするべきなのかと目の前のことだけに集中できるんです
2つ目
「次は〇〇してみる」
失敗してクヨクヨしていても何もしなければ現状は変わりませんからね
どんなに辛くても前を向いて次にやるべきことをとにかくやり続ける
そしたら小さな成功体験を必ず積めるようになるからそれを積み上げていけば大きな成功を掴むことができるよ
3つ目
「いついつまでにやる」
やろうとしていたことが出来なくて自分なんて、なんてダメな人間なんだろうと落ち込んだことないですか?
それっていついつまでにやるって日付を決めて何をやるかまで具体的に決められていないからなんです
あと決めたことはやり抜くこれだけやっていれば結果は後からついてくる

メンタルがしんどいなと思っている方!
現在、体の毒出し整体キャンペーンしてるので是非来てください!
ネット予約はコチラをクリック
Googleマップはコチラをクリック
泉南郡熊取町にある ゆかり整体整骨院が解説する 梅雨の毒出し整体とは?
2024.07.03
吸い玉の効果4選!

①血行の促進
体内に溜まった瘀血というドロドロした血液を浄化し、血行促進する効果が期待できます。
血流の増幅は、リンパの流れを促進し、身体に溜まった老廃物を効果的に流してくれる働きがあります!
血液が運び出す老廃物の大部分は腎臓で分離され、尿として排出されますが、皮膚からも汗や皮脂に混ざって排出されます!
炭酸ガスを強制的に体外に排泄し、新鮮な空気を取り込みやすい状態を作るのも吸玉療法の良さの1つでも有ります!
それによる代謝アップで冷え性やむくみの改善、筋肉の緊張状態の緩和が期待でき、肩こりや腰痛の症状に効果があります!
②内臓の機能を高める
先程説明したように、体内の老廃物を引き出すことで、新陳代謝が高まり内臓機能が活性化します。
消化機能の活性化でダル重さやむくみが解消し、ダイエットにも効果的で、なかなか落とせないセルライトを取り除く効果でも人気ですね!
また「血行促進」という間接的な効果とともに、胃や腸の蠕動運動を助け、消化液の分泌を活発にして消化・吸収・排泄の機能を強める働きがあります!
③アンチエイジング効果
肌を引き上げて刺激を与えることで、肌の細胞を活性化させます!
肌細胞が活性化によりお肌のターンオーバーが早まることで、健康的で若々しい肌に生まれ変わることが期待できます!
血色も良く、明るい肌になります!
④自律神経を整える
自律神経が乱れている(興奮している)状態の神経を落ち着かせる作用があります。

ゆかり整体整骨院では梅雨限定イベント開催中!
ご予約はコチラhttps://reserva.be/yukariseitai
Googleマップはコチラhttps://maps.app.goo.gl/y3avBYE8mTqwjXmk6?g_st=com.google.maps.preview.copy
泉南郡熊取町にある ゆかり整体整骨院が解説する 体の解毒器官の働きは万全ですか?
2024.07.02
体の解毒器官の働きは万全ですか?
肝臓は人体における最大の内臓であり、代謝や解毒、ミネラルやビタミン、血液の貯蔵庫としても働く重要なところです。
日常のストレスや怒り、アルコール類や添加物など様々な処理に働き続けてくれる肝臓を東洋医学的にその肝臓の気を高めてくれるツボの存在があるとしたら知っておきたくないですか?
自分自身でマッサージすることにも使えますね!
ゆかり整体整骨院で受けることができる毒出し整体ではこの肝臓の気を高めることができます!
「大敦」(だいとん)」

写真の赤丸の場所で、足の親指の爪の外側の角にあるツボです。
肝臓にストレスがかかって働きが悪くなっていると、解毒機能が低下し血中に毒素が流れてしまうそんなことの改善に働きかけることで肝臓が元気になり働きがよくなる秘孔です。
しかも、耳鳴りや難聴にも効果ありなんです。
ゆかり整体整骨院ではここをしっかりと網羅した毒出し整体になっています。
病気に変わる前にちょっとした体の疲れとともに内臓の働きを高めるような施術があれば便利です。
病気になってから痛みや休養のリスクを背負って処方箋をもらうのと病気になる前にリスクを背負わずにケアすることができる予防線なら
どちらがいいでしょうか?

処方箋は薬屋さんしか儲かりません…
予約はこちらhttps://reserva.be/yukariseitai
Google情報 ゆかり整体整骨院
https://maps.app.goo.gl/qfj4U19AiqwP32CbA?g_st=com.google.maps.preview.copy
泉南郡熊取町にある ゆかり整体整骨院が解説する 毒出し整体とは?
2024.07.01
こんにちは!
ゆかり整体整骨院です。
季節の移り変わりは早いもので梅雨が明けたら暑い暑い夏が来ますね!
大気や気候の変化とともに体調も急激に変化します!
突然の体調不良の予防や健康維持のために我々は「毒出し」という整体法に辿り着きました!
体に蓄積した毒素を体外に排出すれば新しい新鮮な血液が全身を巡り、ホルモンバランスや自律神経の調整にもつながります。
今回は日頃から毒素を溜めない生活習慣についてお話ししたいと思います。
まず、体内に蓄積した毒素を取り除くには排泄機能を使うことです。
排泄機能として排尿に関係する腎臓、排便に関係する腸が正常に機能することが大切です。
そのために共通して重要になるのが水分です。
1日の水分摂取量としての目安としては食事から1リットル、飲み物から1.5リットルの合計2.5リットルは理想です。
ただし、飲みものからの1.5リットルの水は一度に飲んでも体が吸収できません。
逆に胃に負担をかけてしまうこととなるので、1回の摂取量をコップ1杯分とし何回かに分けて摂取すると体に負担がかかりません。
水を使ったデトックス法は飲むだけではありません。
お風呂でのシャワーも活用できます。
老廃物を集める機関としてリンパ節があります。このリンパ節を刺激し、リンパの流れをよくすることも老廃物を排除する働きになります。
まず温かいシャワーを鎖骨付近にあてます。続いて足のつま先から膝、太もも、股関節へ向かってシャワーを当てます。
次に手の指先から手首、肘、脇の下にゆっくりシャワーを当て、最後にお臍を中心に時計まわりにシャワーを当ててお腹を刺激します。
その他にもお風呂でできるデトックス法として38度から40度のお湯で半身浴をすることもおすすめです。
新陳代謝が上がり発汗により老廃物を排出することができます。
この様に内臓の働きやリンパの流れをよくすることが毒素を溜めない生活習慣として大事です。
これらの作用として自律神経が大きく関係します。
腎臓は特に自律神経の影響を受けやすいので自律神経を調整できる鍼灸治療や東洋医学が毒素が溜まりにくい体質作りには必要です。
当院の「毒出し整体」は東洋医学で太古から使われている吸い玉と浮腫やむくみとして毒素蓄積が現れやすい足部の足底マッサージを併用したどんどん毒素を排出するための施術です。
最近いくら寝ても眠たい、やる気が全く出ないという方!
毒素に体を蝕まれている可能性がありますよ!

↓ご予約はコチラ↓
https://reserva.be/yukariseitai
https://maps.app.goo.gl/qfj4U19AiqwP32CbA?g_st=com.google.maps.preview.copy
↑地図はコチラ↑